HPLCの上手な使い方
Ⅱ章-5 イオン対試薬について
緩衡試薬と同様にHPLCの溶離液中に添加する試薬として、イオン対試薬というものがあります。前頁でもこの試薬に関して若干触れていますが、ここでは原理から使用条件までもう少し詳しく説明したいと思います。
イオン対試薬とは
酸や塩基などがイオン的に解離すると、非常に水に溶け易くなるため、ODSに代表される逆相系の充填剤にはほとんど保持されなくなってしまいます。このような化合物と溶離液中でイオン結合させる試薬をイオン対試薬といいます。したがって、サンプルが酸性であれば塩基性のイオン化合物が、逆にサンプルが塩基性であれば酸性のイオン化合物がそれぞれイオン対試薬に相当します。この試薬を溶離液中に添加すると、異符号のイオン同士がお互いに引き合って中性のイオン対を形成し、溶離液中でのサンプルの解離が抑制されます。また、イオン対試薬にはさまざまなアルキル基が結合されているため、形成したイオン対はより脂溶性が強くなり、その結果ODS充填剤などへの保持が増大します。例として、両性イオン化化合物であるアミノ酸と、この試薬とがイオン対を形成する様子を下図に示します。
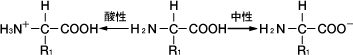
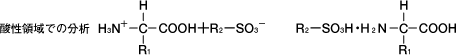
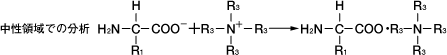
図にも示したように、アミノ酸などの両性化合物は酸性領域ではアミノ基が解離していますが、中性領域に近づくにつれてカルボキシル基が解離してくるため、分析を行うpHによってイオン対試薬の種類を変える必要があります。
溶離液のpH
イオン対分析を行う際の溶離液のpHは、その溶離液中でサンプルと試薬とがほぼ完全にイオン解離し、さらに解離したイオン同士が容易にイオン対を形成するように設定する必要があります。対象サンプルによっても異なりますが、酸性化合物を分析する場合はpH6.5~7.5、塩基性化合物を分析する場合はpH2.5~3.5を目安として溶離液を調製してください。
イオン対試薬の種類
イオン対分析に使用する試薬としては、前述したように溶離液中でほぼ完全に解離しなければならないため、イオン解離性の強い化合物を選ぶ必要があります。また、充填剤への保持に関与する疎水性基に関しても、サンプルの検出を妨げないように、直鎖アルキル基などの紫外吸収が無い官能基が一般的です。以下に、通常よく使用されるイオン対試薬をまとめましたので試薬選択の際の参考にしてください。
| 試薬名 | 分子量 | 対イオン | |
|---|---|---|---|
| 塩基性試料 | ペンタンスルホン酸ナトリウム ヘキサンスルホン酸ナトリウム ヘプタンスルホン酸ナトリウム オクタンスルホン酸ナトリウム ドデカンスルホン酸ナトリウム ドデシル硫酸ナトリウム(SDS) |
M.W. 174.2 M.W. 188.2 M.W. 202.2 M.W. 216.3 M.W. 272.4 M.W. 288.4 |
CH3(CH2)4SO3- CH3(CH2)5SO3- CH3(CH2)6SO3- CH3(CH2)7SO3- CH3(CH2)11SO3- CH3(CH2)11OSO3- |
| 酸性試料 | テトラエチルアンモニウム水和物 テトラブチルアンモニウム水和物 テトラブチルアンモニウム塩化物 テトラブチルアンモニウム臭化物 トリヘキシルアミン トリオクチルアミン |
M.W. 147.3 M.W. 259.5 M.W. 277.9 M.W. 322.4 M.W. 269.5 M.W. 353.7 |
(C2H5)4N+ (C4H9)4N+ (C4H9)4N+ (C4H9)4N+ (C6H13)3N (C8H17)3N |
また、酸性試料用試薬・塩基性試料用試薬ともに数種類のアルキル鎖のものがありますが、一般的にアルキル鎖の長い試料ほど保持が強くなります。目的成分と他成分との分離が不充分な場合には、違うアルキル鎖の試薬を使用することにより分離が改善される可能性があります。その一例として、C6・C7・C8の側鎖を持つアルキルスルホン酸ナトリウムをイオン対試薬として用い、4成分のアミノ酸の分析を行った結果を右に示します。図より、試薬のアルキン鎖が長くなるほど、どの成分も保持が増大し、各成分の分離が良くなっていることがわかります。
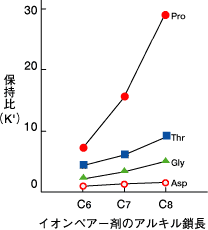
| Asp | :アスパラギン酸 |
|---|---|
| Gly | :グリシン |
| Thr | :トレオニン |
| Pro | :プロリン |
イオン対試薬の種類
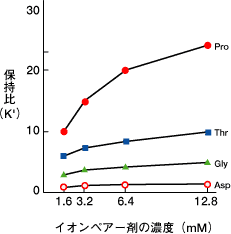
次にイオン対試薬の濃度についてですが、基本的には解離したサンプルとイオン化した試薬とは1:1でイオン対を形成するため、目的成分と等モル量の試薬を溶離液中に添加すればいいことになります。ところが、分析サンプル中に目的成分以外のイオン性化合物が存在していると、イオン対試薬がこの化合物とイオン対を形成してしまうため、目的成分が充分に保持されなくなってしまいます。さらに場合によっては、ピークのリーディングやピーク割れ等の現象が起こることもあります。したがって、イオン対試薬の濃度としては、分析サンプル中のイオン性化合物の総モル数に対して常に過剰になるように設定してください。また、一般的にイオン対試薬の濃度が高くなるとサンプルの保持が増大するといわれていますが、右図にその例を示します。ヘプタンスルホン酸ナトリウムの濃度を変化させて、前頁と同じアミノ酸の保持挙動を比較したところやはり試薬濃度が高くなるにつれて、保持が強くなる傾向が見られました。この結果より、試薬の種類を変えなくても、試薬濃度を変化させることで分離が改善できる可能性があることがわかります。
イオン対分析を行う際の注意点
- イオン対分析を行う際には、目的成分と他の成分との分離や分析時間などを考慮し、試薬の種類および濃度に関して充分な予備実験が必要となります。
- 濃度に関しては、分析オーダーでは通常5mM~20mM程度で使用しますが、濃度がくなるほど充填剤の劣化が早くなりますので、分析可能な範囲で、できるかぎり薄い濃度を選択してください。
- サンプルを大量に注入する場合には、イオン対試薬の濃度も濃くしてください。
- 緩衡液と同様に、分析終了後には必ずカラム洗浄を行ってください。特に長期間カラムを使用しない場合などは、試薬の析出によるカラム劣化が起こる可能性がありますので充分に洗浄してください。





































